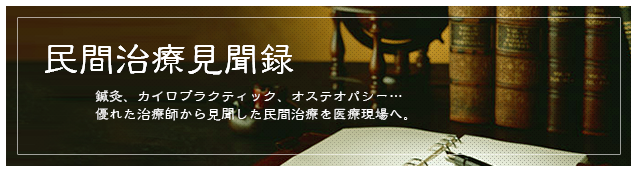第16話「柔道整復術」
柔道の源流に柔術という武術がある。柔道に比べて関節技が多く激しい格闘技だ。この武術の中で殺法という相手を死傷させる技と同時に活法という治療する技が生まれた。この活法を行う治療法がほねつぎと呼ばれる柔道整復術になる。
ある市の柔道連盟の理事が柔道場を経営していて、その道場に併設された接骨院を見学にいったことがある。畳の引かれた道場の奥にある接骨院を見て、これこそ柔道整復術の原点だと感じた。治療を見せてもらえたが、患者への治療は電気を当てたり、マッサージをしたりとごく平凡なものだった。
しばらくして柔道整復師の資格を持つ若者が私のクリニックで働きたいというので、雇って自由にやらせてみた。恥ずかしい話だが、私はそれまで柔道整復の治療の中で、保険でできる治療範囲が骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷だけだということを知らなかった。多くの整骨院が腰痛を腰椎捻挫などと称して保険を請求していることも知らなかった。
昔はカリスマ的な柔道整復師がいたらしい。ところが保険で治療費を請求できるようになり、技術的な向上を望む人が少なくなったのか、凄腕の人を見たことがない。柔道整復師になるためには柔道が必須の科目になっているが、形式的に学んでいるだけだ。
どんな治療でもそうだが、保険が適応されると治療費が三分の一から十分の一で済むようになる。そうなると患者さんは、多少でも効けばいいやといった感じで治療に来るから施術する側の腕は上がらなくなる。鍼灸やマッサージでも医者が意見書を提出すれば、一定金額までの治療には保険が適応される。だが、保険で出来る治療の範囲は限られてくる。施術する側はなるべく保険内の安い金額で患者さんを治療しようとするので、沢山の患者さんをこなす必要ができてくる。
こういった状況ではゆっくり患者と向き合う時間が無くなり、名人芸は生まれにくくなる。さらに近年、柔道整復師養成施設が14校から100校にふえて資格者の急増と共にますます腕のいい先生はいなくなってしまった。
考えてみると、柔術の稽古をしているときに骨折、脱臼、捻挫は頻回に起こったはずだ。
ご存じのように柔術には関節技が多くあるので、関節をねじ上げると脱臼や捻挫が起こる。また投げ技を使うと当然骨折も起こってくる。
こういった殺法で起こった怪我をその場で治していたから、骨折は徒手整復してから副木で固定する、捻挫も正しい位置に入れてから固定することが行われていた。
しかし、現在は診断にはレントゲンが必要になり、医療における損害賠償などが問題になってくると、たとえ上手に治すことができてもまずは整形外科でレントゲンやCTを取ってもらうことになる。そうなると処置はどうしても整形外科の先生がやることになる。外傷に関する治療は整形外科抜きでは治療が出来ない状況になってきている。
つまり、柔整師が腕を磨く場所が減ってきているのだ。
さらに柔道整復術は外からの力、つまり外力によって骨折、脱臼、捻挫がおこった場合の治療法だが、体の中からの変化、つまり老化によっておこった骨折、変形性膝関節症、ヘルニアなどとは厳密に区別して治療しなければならない。
往々にして外力による病変の治療術は、体の中からの変化の治療には使えない。このことを勘違いしている人が多い。
例えば、変形性膝関節症は膝の軟骨がすり減ったのが原因だと考えられている。しかし、筋力の弱い女性に多い事、労働の激しさとは関係ない事などから、筋力が弱くて骨格を正しく保てないのが原因と私は考えている。
つまり、骨格の歪みから関節が捻じられたまま曲げ伸ばしすることで軟骨が減ってしまうのだ。そういう考えで治療するとよくなる。
つまり、外傷の時とは治療も理論も違うことになる。
整形外科の治療は、関節内への注射、シップそして最終的には手術しかない。柔道整復術は外力による障害を治す治療として発達してきたから、体の中から起こってくる病気には弱いのだ。
柔道整復師にもカリスマ的な腕を持つ人もいるだろうと思う。だが外傷のスペシャリストの地位は整形外科医に奪われてしまった。
柔道整復の技である外力からの障害を治す技術を応用して、体の中からの障害を治す治療に変化をさせていくには、一人一人の患者に十分な時間をかける必要があるが、現状では多くの患者をこなさなければならない。つまり研究の時間が十分に取れにくい状態にある。
時代に適応するために多くの若い柔道整復師の先生は新しい道を模索しているのだろうと思う。
- 第16話「柔道整復術」
- 2016年07月01日
「民間治療見聞録」目次
- 第1話 民間治療にのめり込むきっかけになった話(2015.11.01)
- 第2話 体を触ることで内臓疾患が治るか?(2015.12.01)
- 第3話 民間療法は現在の医療より進んでいたのか?(2015.12.15)
- 第4話 民間治療の分類(2016.01.04)
- 第5話 鍼治療(2016.01.15)
- 第6話 灸による治療(2016.02.01)
- 第7話 耳鍼、水晶鍼(2016.02.15)
- 第8話 井穴鍼(せいけつしん)(2016.03.01)
- 第9話 体から血を吸いだし(刺絡 瀉血)、内出血させて治療する(吸角)(2016.03.15)
- 第10話 武道家のマッサージ師(2016.04.01)
- 第11話 レントゲン技師だったマッサージ師の治療(2016.04.15)
- 第12話 ストレッチとリンパマッサージ(2016.05.01)
- 第13話 お寺で発達した整体術(2016.05.15)
- 第14話 カイロプラクティックと環椎(2016.06.01)
- 第15話 オステオパシー(2016.06.15)
- 第16話 柔道整復術(2016.07.01)
- 第17話 気功(2016.07.15)
- 第18話 気功と佛眼(2016.08.01)
- 第19話 催眠療法、野口整体、Oリングテストなど(2016.08.15)
- 第20話 内蔵疾患から背中が歪むことがあるか?(2016.09.01)
- 第21話 骨格は歪んだり治ったりしている(2016.09.15)
- 第22話 医療にするための方法論(2016.10.01)
- 第23話 整体で病気を予防できる(2016.10.15)
- 最終話 最後に(2016.11.01

患者さまお一人お一人にゆっくり向き合えるように、「完全予約制」で診察を行っております。
診察をご希望の方はお電話でご予約ください。
- 読み物 -
- ●2026.01.01
- 第353回「ラクダ、馬、象にも乗ったことがある」
- ●2025.12.25
- 第352回「夜の散歩という絵」
- ●2025.12.20
- 第351回「下肢の浮腫みとコムラ返り」
- ●2025.12.10
- 第350回「東京は貧しい人と豊かな人が混じり合って暮らしている」
- ●2025.12.01
- 120.牛黄【ゴオウ】
お知らせ
- ●2025.10.28
- オステオパシーの勉強会
- ●2025.05.02
- 背骨ローラーの販売について
※ページを更新する度に表示記事が変わります。