第272回「娘のために漢方の丸薬を作って欲しい」
【漢方丸薬だけは飲める】
煎じ薬やエキス漢方はまずくて飲めない
東京で何十年も漢方医をされている開業医がお嬢さんを連れてやってきた。体力のなさや過食で困っているという。そこで防風通聖丸を出したら元気になり、体重も落ちた。丸薬は飲みやすくていいという。
すると開業医の先生は、お嬢さんに以前から自分が使ってみたい薬があるのだが、煎じ薬やエキス漢方薬はまずいと言って飲んでくれない。自分がお嬢さんの症状に効くと思っている処方を丸薬で作って欲しいという。
その先生は煎じ薬での治療を専門にしているから、丸薬も簡単に作れると思ったのだろう。
お父さん先生が希望する13種類の生薬からなる処方
お父さん先生の希望する処方
柴胡(サイコ)、竹筎(チクジョ)、茯苓(ブクリョウ)、麦門冬(バクモンドウ)、陳皮(チンピ)、枳実(キジツ)、黄連(オウレン)、甘草(カンゾウ)、半夏(ハンゲ)、香附子(コウブシ)、生姜(ショウキョウ)、桔梗(キキョウ)、人参(ニンジン)
丸薬を作るためには生薬を粉にしなければならない。
生薬を粉末にした500g入りのパックも売られているが、すべての生薬末が売られているわけではない。いくつかの生薬末は売られていないので、自分で粉にしなければならない。
ハンマ―ミルという小さな粉砕機で粉にして細い篩を通るほどに細かくする。また麦門冬のような粘着性のある生薬は粉末にはできないので、煎じた液を、丸薬を作るときの水替わりする。そのためには生薬を煮詰める寸胴が必要だ。

ハンマ―ミルと篩

生薬を煮詰めるのにはIHでタイマーの付いたものを使う
丸薬つくりの難しいところは毎回、同じように丸薬ができるとは限らないこと
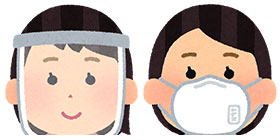
ゴーグルとN95のマスクをして丸薬を作る
同じ処方で丸薬を作っても生薬の性質によって丸薬がどうしてもできないことがある。
生薬の収穫時期、産地によって粘り気のあるものや、そうでないものがあり、うまく丸薬にならないときは、初めから作り直さなければならず、その場合は作りかけの丸薬は捨てる以外に方法がない。また刺激性のある生薬の時は、喉と目に刺激が来るので、マスクとゴーグルが必要になる。
 同じ紫根という生薬末でもロットによってこれだけ色が違う。薬を使った効果は一緒だが、生薬末の粘り気なども随分違う。
同じ紫根という生薬末でもロットによってこれだけ色が違う。薬を使った効果は一緒だが、生薬末の粘り気なども随分違う。
丸薬工場の多くが閉鎖している
丸薬作りは労働集約型の仕事で人件費がかかり、作るのがきわめて難しい。さらに医薬品を作っている会社では厚生労働省が新薬のような基準を当てはめようとするので、製造許可の更新時期になると丸薬作成の経験のない担当者がとんでもないことを言い出すので、メーカーは困っている。
さらに円安で材料費が上がり採算が取れなくなっている。
丸薬をつくるのには戦略が大切
漢方医のお父さんの処方を分析してみると、元気を出すのは人参しかなく、過食に効きそうなものは柴胡、竹如しかない。特に元気を出す人参は3gしか処方されていない。人参だけの丸薬を作り、投与すると良く効く。
私が200種類以上の丸薬を作ってきたからといって、傷寒論や金匱要略の処方を使ってはいない。処方のなかの良く効く成分だけをとりだしていろんな病気に効く薬を作っている。
煎じ薬は飲んでくれない
生薬を煎じるという方法は、紀元前から使われている消毒を兼ねた抽出法だが、まずくて手間がかかるから、誰も続けては飲んでくれない。
手間も費用もかかるが、薬は続けて飲めるものでないと意味がない。
- 第272回「娘のために漢方の丸薬を作って欲しい」
- 2023年05月20日
香杏舎ノート の記事一覧へ

患者さまお一人お一人にゆっくり向き合えるように、「完全予約制」で診察を行っております。
診察をご希望の方はお電話でご予約ください。
- 読み物 -
- ●2026.01.01
- 第353回「ラクダ、馬、象にも乗ったことがある」
- ●2025.12.25
- 第352回「夜の散歩という絵」
- ●2025.12.20
- 第351回「下肢の浮腫みとコムラ返り」
- ●2025.12.10
- 第350回「東京は貧しい人と豊かな人が混じり合って暮らしている」
- ●2025.12.01
- 120.牛黄【ゴオウ】
お知らせ
- ●2025.10.28
- オステオパシーの勉強会
- ●2025.05.02
- 背骨ローラーの販売について
※ページを更新する度に表示記事が変わります。










