第131回「筋肉トレーニングのウソ」
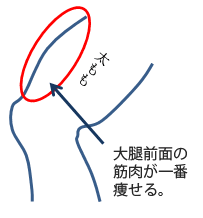 30歳と80歳になった時の筋肉を比べると、筋肉は30歳の時の7割~8割ほどに痩せていく。一番痩せるのが太もも前面の筋肉で約半分になる。この筋肉は膝を伸ばす筋肉で、これが痩せるとしゃがんだ状態から立つのが辛くなる。
30歳と80歳になった時の筋肉を比べると、筋肉は30歳の時の7割~8割ほどに痩せていく。一番痩せるのが太もも前面の筋肉で約半分になる。この筋肉は膝を伸ばす筋肉で、これが痩せるとしゃがんだ状態から立つのが辛くなる。
同じカロリーの食事をしていても中年太りになるのは筋肉が痩せてくるからだという。筋肉はカロリーを沢山消費する臓器で、筋肉の量が大きければ大きいほど消費するカロリーも多い。肉が痩せるにしたがって消費カロリーが減り、その余ったカロリーが脂肪として蓄えられる。
ある大学の教授が筋肉トレーニングはダイエットによいと言い出した。筋肉トレーニングで太らない体づくりができる、筋肉量が多くなれば筋肉がカロリーを消費するから太らない。教授自身がボディビルダーで自分の経験からもそう主張していた。
筋トレを始める
なるほど筋肉が増えれば足腰も丈夫になり、ダイエットにもいい、一石二鳥だと思い試してみることにした。
筋肉量を増やすにはきちんとしたトレーニング理論が確立されている。まず1週間に2回筋肉トレーニングをすれば十分なこと、それ以下では筋肉がつかないが、かといって毎日筋肉トレーニングをしても筋肉量は増えない。筋肉に与える負荷は最大筋力の7~8割をかけること。腕の上腕2頭筋を鍛えるのなら7~8回続けてバーベルを持ち上げられる力がそれにあたる。これを2~3セットすれば十分だ。
基本的な理論を学んだところで仕事の後にジムに通い始めた。3~4か月すると次第に筋肉がつきだした。力を入れると筋肉のスジがみえるようになってきた。筋肉が増えていくのが楽しくて少しずつ荷重を増やしていった。
ある時トレーニングで首を傷めた。重いバーベルを持って腕の筋肉を鍛えていた。歯をくいしばっていると首にも力が入り、首の筋を傷めてしまったのだった。
1年が経ち、トレーニング回数が100回を超えるころからかなり疲労を覚えるようになった。トレーニングが負担になっているのは明らかだが、回数を減らすと筋肉が痩せ、負荷を減らせば現状維持になってしまう。仕事をしながらの筋トレは結構きついことが分かった。
一人の真実がすべての人に当てはまるわけではない
2年が過ぎ回数が200回を超えるころから疲労困憊するようになった。食べても太らず5キロほど体重が落ちた。何か病気ではないかと検査をしたが異常はなかった。そのうちに原因不明の関節炎が起こり、副鼻腔炎にもなった。疲労から免疫が落ちたことは明白だった。結局256回でトレーニングを中止した。関節炎は西洋医学では治らず自分で作った薬がよく効いた。副鼻腔炎は大学病院で手術が必要と言われたがこれも自分の薬で治すことができた。
私にはダイエットが出来るほどの筋肉量をつける体力がないことが分かった。その教授にはできても私にはできないことだった。つまり一人の健康法はすべての人の健康法にはならないのだ。トレーニングを止めると太くなった筋肉は風船がしぼむように急速に細くなった。
専門家に相談する
私の叔父は医者だがオリンピックの候補に選ばれるほどのスポーツ好きだ。歳を取ってもラグビー、テニス、アメフトなどを楽しんでいた。後年、大手スポーツメーカーの顧問になり、80歳を過ぎてもバスケットのコーチをしていた。
叔父は私の話を聞くなり「アホか!お前の趣味はゴルフだろ。そうなら幾つの年になってもゴルフが楽しめるように体を鍛えればいい。それ以上のトレーニングは意味がない」と言った。
話を聞きながら私はトレーニングを始めて4~5か月で190ヤード近いパー3で3番アイアンが打てるようになったことを思い出した。50代後半の私でもロングアイアンが打てることが楽しかった。
叔父が言いたいことは、トレーニングは明確な運動の目的をもってするもので、ダイエットとか健康になりたいとか漠然とした目的でやるものではないということだ。ダイエットだけが目的なら筋肉をつける運動より燃焼系の運動のほうがいいだろうが、それも明確な目的がなければ続かない。
人は日常、自分が必要とする筋力しか維持できない。普通のサラリーマンなら歩いたり、階段を上がったりバックを持つ筋力しか維持できない。筋肉を沢山つけたところで病気になればすぐに失われてしまうし、筋肉量が多い人が長生きしたという証拠もない。特段トレーニングをしなくても日常よく歩いたり、エスカレーターに乗らず階段を上がるだけで十分ではないのだろかと思う。
ただし、成長期に筋肉を鍛えるとそれは一生の財産になるのも事実だと思う。
2013年9月 87歳の叔父は、70年以上現役のバスケットボール選手を続けてきたことにより、日本体育協会から三浦雄一郎氏などとともに表彰されました。
天皇陛下からもお言葉をいただいたと聞いております。
- 第131回「筋肉トレーニングのウソ」
- 2013年10月21日
香杏舎ノート の記事一覧へ

患者さまお一人お一人にゆっくり向き合えるように、「完全予約制」で診察を行っております。
診察をご希望の方はお電話でご予約ください。
- 読み物 -
- ●2026.01.25
- 第355回「日本は原子力潜水艦を持つべきだ」
- ●2026.01.20
- 第354回「DICに牛黄は使えないか?」
- ●2026.01.01
- 第353回「ラクダ、馬、象にも乗ったことがある」
- ●2025.12.25
- 第352回「夜の散歩という絵」
- ●2025.12.20
- 第351回「下肢の浮腫みとコムラ返り」
お知らせ
- ●2025.10.28
- オステオパシーの勉強会
- ●2025.05.02
- 背骨ローラーの販売について
※ページを更新する度に表示記事が変わります。










