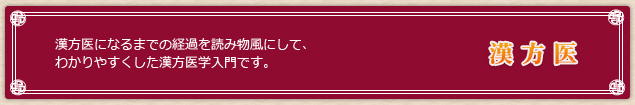第7話「処方の解析に丸剤を使う」
山本先生は漢方の古典の中から現代の病気に効く処方を選び出してきてそれを我々に分かりやすく解説してくれた。処方を選び出す際、西洋医学の薬で簡単に治る病気の処方を選び出しても感謝されない。だから西洋医学で治りにくい病気に効く処方を選んで我々に教えてくれた。この山本先生が教えてくれた処方の解析に丸剤がどう役に立つかを具体的にみていこう。
補中益気湯(ほちゅうえっきとう)という薬を例に取って説明したい。まずは、この薬の出来上がってきた過程、山本先生の解説、そして丸剤による分析の順で説明してみよう。
補中益気湯に含まれる生薬
黄耆(おうぎ)、人参(にんじん)、白朮(びゃくじゅつ)、甘草(かんぞう)、
当帰(とうき)、陳皮(ちんぴ)、升麻(しょうま)、柴胡(さいこ)、
大棗(たいそう)、生姜(しょうきょう)
古代中国で一番問題になった病気は感染症であった。腸チフス、コレラなどが伝染すると手がつけられない。感染を防ぐために道路を閉鎖し、感染した村々を焼きはなった。こういう伝染病を治す薬として作られたのが葛根湯であった。ところが感染症でなくても致死率の高い病気があった。紀元700年頃、モンゴル軍に囲まれた城の中でバタバタ人が死んでいった。周りをモンゴル軍が囲っているから伝染してくる感染症ではない。現代医学で考えると死亡原因は栄養失調だったと思われるが、ともかくその状態を薬で何とか治そうと李東垣(りとうえん)が補中益気湯を作った。この薬は体の元気を高める作用と筋肉の緊張を高める作用を持っている。この薬がどのくらい役に立ったかは不明だが、この処方の使い方について山本先生は病後の体力低下、夏負けや脱肛、胃のアトニ―、子宮脱などに使えばいいと教えてくれた。
考えてみると、元気を出す治療は現代医学にもある。点滴やビタミン剤などだ。この薬を本当に現代に生かそうと思えば、現代医学にない作用に注目しなければならない。それは筋肉の緊張作用を高める作用だ。西洋医学にはそういう作用を持つ薬がないので、例えば脱肛が治ればそれは漢方として大変重要な処方になる。夏負けや病後の体力低下によく効いても、クーラ―や点滴のある時代ではその処方の良さをなかなか理解してもらえないことは想像に難くない。
以前、学校の校長先生が脱肛で私の診療所を受診した。山本先生に教わった通り補中益気湯を出したが効かない。2-3倍量を飲むように指示したら「肛門がするする持ち上がって気持ちがいい」と言う。脱肛を治す補中益気湯の中の成分は柴胡、升麻だと言われている。もしそうなら柴胡と升麻だけの丸薬を作ればもっと効くかもしれない。ひょっとするとそれ以外の成分が効いている可能性もある。そこで柴胡、升麻、黄耆、枳実、肉蓯蓉など筋肉を強くすると言われている生薬を加減して西洋医学にない強い効果を持つ丸剤を作り上げた。
 一般の人は漢方の古典を読めば専門家になれると思っているかもしれないが、なかなかそうはいかない。最近、漢方メーカーが老人性痴呆にいいと宣伝している抑肝散(よくかんさん)という薬がある。この薬が昔どんなふうに使われていたかというと、引きつけを起こした子供に使う。それも胃の中に水が溜まった状態の時に使うと書いてある。使う場合は母子同服、つまりお母さんも子供と一緒に薬を飲むことになっている。これがどんな病態か現代の我々には想像さえ出来ない。こういった処方の中から現代医学にない薬を作り出していくことが丸剤にはできるのである。ちなみに保険の通常量で抑肝散が痴呆に効くとは私には思えない。
一般の人は漢方の古典を読めば専門家になれると思っているかもしれないが、なかなかそうはいかない。最近、漢方メーカーが老人性痴呆にいいと宣伝している抑肝散(よくかんさん)という薬がある。この薬が昔どんなふうに使われていたかというと、引きつけを起こした子供に使う。それも胃の中に水が溜まった状態の時に使うと書いてある。使う場合は母子同服、つまりお母さんも子供と一緒に薬を飲むことになっている。これがどんな病態か現代の我々には想像さえ出来ない。こういった処方の中から現代医学にない薬を作り出していくことが丸剤にはできるのである。ちなみに保険の通常量で抑肝散が痴呆に効くとは私には思えない。
丸剤を用いて沢山の薬を解析してきたおかげで随分と生薬に詳しくなり、難病にも効く薬を作ってきた。丸剤を作るという作業は漢方を解析する手段であり、日本の漢方を世界的な医療にできる大変いい方法なのである。
- 第7話「処方の解析に丸剤を使う」
- 2013年04月26日
「漢方医<後編>」目次
- 第1話「丸剤を知るきっかけとなった本との出会い」(2013.03.15)
- 第2話「モンゴル医学とは」(2013.03.22)
- 第3話「山本巌先生から癌を治す処方を伝授される」(2013.03.29)
- 第4話「製丸機を買う」(2013.04.05)
- 第5話「丸剤を作ることへの様々な障害」(2013.04.12)
- 第6話「山本先生亡き後、漢方の発展を考える」(2013.04.19)
- 第7話「処方の解析に丸剤を使う」(2013.04.26)
- 第8話「一般の医者は漢方を信じていない」(2013.05.03)
- 第9話「保険漢方の普及が漢方医の首を絞める」(2013.05.10)
- 第10話「新しい薬を作らない漢方医たち」(2013.05.17)
- 第11話「技を伝承する難しさ」(2013.05.24)
- 第12話「先人たちからの遺言」(2013.05.31)
- 第13話「絵とフェイスタイム(FaceTime)」(2013.06.07)
- 第14話「東京へいく決心をする」(2013.06.14)
- 第15話「東京の調査」(2016.01.25)
- 第16話「東京人って本当にいるの?」(2016.04.25)

患者さまお一人お一人にゆっくり向き合えるように、「完全予約制」で診察を行っております。
診察をご希望の方はお電話でご予約ください。
- 読み物 -
- ●2026.01.20
- 第354回「DICに牛黄は使えないか?」
- ●2026.01.01
- 第353回「ラクダ、馬、象にも乗ったことがある」
- ●2025.12.25
- 第352回「夜の散歩という絵」
- ●2025.12.20
- 第351回「下肢の浮腫みとコムラ返り」
- ●2025.12.10
- 第350回「東京は貧しい人と豊かな人が混じり合って暮らしている」
お知らせ
- ●2025.10.28
- オステオパシーの勉強会
- ●2025.05.02
- 背骨ローラーの販売について
※ページを更新する度に表示記事が変わります。