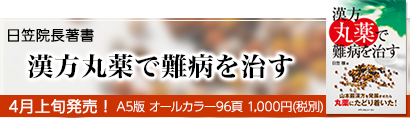第214回「ネットから本へ」
もう25年以上、香杏舎ノートを毎月、書いてきた。少しでも漢方や養生を分かってもらおうと始めたものだ。
最初はA4の紙の裏表に印刷していたので、おおよそ原稿用紙4枚分の1600字に合わせるように書いて受付の前に置いていた。患者さんは毎月出る原稿を集める人もいて、バックナンバーが欲しいといわれると、ずいぶん前のものも置いておかねばならなかった。
それから10年以上経ってくるとPCが家庭にも置かれるようになり、原稿の字数制限がなくなって、ずいぶんと気楽に原稿を書けるようになった。カラーの写真もふんだんに入れたHPを書き始めた。患者さんはとても詳しく読んでくれるようになったので、日本漢方と中医学の違いなども詳しく書けた。
スマホによる字数制限
5年くらい前からほとんどの人がスマホを見るようになって、長い文章は読まれないことがはっきりしてきた。スマホの1画面から2画面に入る程度の原稿でなければ読んでくれない。おそらく原稿用紙2枚分以下だろう。Facebookやtwitterがよくみられるようになると、読まれる文字はますます少なくなった。ツイッターの文字制限は日本語の場合140字だ。この量だと内容の深い話はできない。読んでもらうためには衝撃的な話だとか自己主張をぶつけるといった、本人にとって衝撃的な原稿しか書けない。
私が掲載をお願いしているホームページビルダーさんはとてもよく仕事をしてくれる。図などを使用する場合も著作権をチェックしてくれる。ある時、原稿を送るとこの部分は省いていいかと聞いてきた。全体のブログの流れの中では問題ないものでも、最近は詳しく原稿を読まない人が多いので、炎上してしまうことがあるという。確かに私もスマホでブログを読むときに長い記事は飛ばし読みする癖がついていることに気がついた。
情報理論では情報が多すぎるときは雑音になるというのがある。確かに多すぎる情報は雑音だ。ネットにはフェイクニュースがあり、些細な怒りが増幅した情報もある。正確な情報は意外に少ないし、選別するのが難しい。
ネットから本へ
出版会社の社長と話をする機会があった。
その人は「これからも情報伝達の手段として本の重要性は変わりがない。」という。
たしかに考えてみると、出版には金がかかるからフェイクニュースは本にはできない。自分の怒りを本にしようとしても印刷しているうちに怒りは冷めてしまう。衝撃をねらうような記事は本としての価値がない。
もし情報を正確に相手に伝えたいなら紙に印刷するしかないのだろうと思うようになった。
- 第214回「ネットから本へ」
- 2020年03月20日
香杏舎ノート の記事一覧へ

患者さまお一人お一人にゆっくり向き合えるように、「完全予約制」で診察を行っております。
診察をご希望の方はお電話でご予約ください。
- 読み物 -
- ●2026.01.25
- 第355回「日本は原子力潜水艦を持つべきだ」
- ●2026.01.20
- 第354回「DICに牛黄は使えないか?」
- ●2026.01.01
- 第353回「ラクダ、馬、象にも乗ったことがある」
- ●2025.12.25
- 第352回「夜の散歩という絵」
- ●2025.12.20
- 第351回「下肢の浮腫みとコムラ返り」
お知らせ
- ●2025.10.28
- オステオパシーの勉強会
- ●2025.05.02
- 背骨ローラーの販売について
※ページを更新する度に表示記事が変わります。