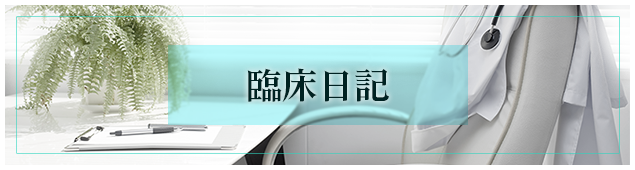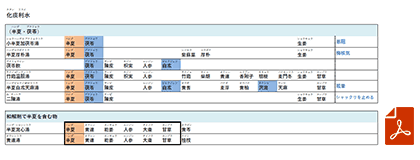【 漢方・整体施術 治療症例 】
71.咳と痰で眠れない
咳と痰が出て困っている。診察中も痰があふれるように出て、時々ティッシュに痰を出す。幾つかのクリニックに行ったが、原因不明だった。咳が出て20分に一度くらい痰を出すが、夜寝ると特にひどくなり、睡眠不足が続いている。詳しく話を聞くと、右を上に横に向いて寝ると少しましになるという。ふと、右肺の気管支拡張症ではないかと思った。
痰飲(たんいん)という病気
痰飲とは漢方の病態を示す用語で、消化管の吸収障害にともなって発生する溜飲(振水温・グル音として聴取する)あるいは肺の分泌増大による多量の喀痰などをいう。簡単に言うと粘液状のものが口から出る状態をいう。
 山本巌先生によれば、痰というのは難しい概念で、脳梗塞で麻痺を起こし、嚥下障害から痰を飲み込めない状態になり、口から泡を吹いているような時、「脳に痰が詰まった」と古代の中国人は判断したらしい。口から出る液体は気管から上がってくる、いわゆる痰もあるが、胃から上がってくる粘液状の液体もある。半夏は呼吸器の病気にもそして消化器の病気にも使われる。半夏の去痰作用や胃をよくする作用は知っているが、どんな状況に使えるかは分からない。
山本巌先生によれば、痰というのは難しい概念で、脳梗塞で麻痺を起こし、嚥下障害から痰を飲み込めない状態になり、口から泡を吹いているような時、「脳に痰が詰まった」と古代の中国人は判断したらしい。口から出る液体は気管から上がってくる、いわゆる痰もあるが、胃から上がってくる粘液状の液体もある。半夏は呼吸器の病気にもそして消化器の病気にも使われる。半夏の去痰作用や胃をよくする作用は知っているが、どんな状況に使えるかは分からない。
半夏だけで効くのか
この患者さんの病態はまさに痰飲の状態なので、痰を取るために半夏がよさそうだと思った。ただ半夏を含む二陳湯といった処方になると何が効いているのか分からなくなるので、半夏だけの作用を見てみる必要がある。
そこで半夏だけの丸薬を作ろうとしたが、とても困難だった。半夏は里芋科に属する生薬で粘りがあるからだ。
なんとか丸薬を作り、飲んでもらったら咳も痰も1週間でまったく消えてしまった。今後は半夏の丸薬の作り方を研究して色々と試してみたいと思っている。
(9301)
丸薬の賦形剤
丸薬を固める糊として米が使われる。もち米に熱を加えてお餅にしてから粉にしたものを寒梅粉(かんばいこ)といい、強力な糊として使われる。その糊の効果を弱めるためにうるち米(普通の米粉)を使う。粘り気を出さないために熱を加えていない米粉の状態で使う。
単味の生薬の丸薬作りは難しい。特に地黄、蘇木、釣藤鈎は難しい。半夏の難しさは半夏そのものが餅のようにのびることだ。半夏の丸薬には硫黄と半夏を混ぜ合わせた半硫丸があるが、硫黄が入ることでまったく違う薬になってしまう。丸薬を作るためには粘り気を落とす賦形剤を考えなければならない。
なお生半夏は毒性が強く、生姜によって修治(*加工)した姜半夏が使われる。
*修治(しゅうじ)とは
生薬の毒性を弱めたり、効果を高めたりする加工作業のこと。
- 【 漢方・整体施術 治療症例 】
71.咳と痰で眠れない - 2022年05月01日

患者さまお一人お一人にゆっくり向き合えるように、「完全予約制」で診察を行っております。
診察をご希望の方はお電話でご予約ください。
- 読み物 -
- ●2026.02.01
- 121.腹水
- ●2026.01.25
- 第355回「日本は原子力潜水艦を持つべきだ」
- ●2026.01.20
- 第354回「DICに牛黄は使えないか?」
- ●2026.01.01
- 第353回「ラクダ、馬、象にも乗ったことがある」
- ●2025.12.25
- 第352回「夜の散歩という絵」
お知らせ
- ●2025.10.28
- オステオパシーの勉強会
- ●2025.05.02
- 背骨ローラーの販売について
※ページを更新する度に表示記事が変わります。