第261回「補中益気湯(ほちゅうえっきとう)の解析」
古代中国で一番問題になった病気は伝染病であった。伝染病が発生すると手がつけられない。感染を防ぐために道路を閉鎖して感染が広がらないようにした。今でも中国ではコロナを防ぐためにゼロコロナ政策というロックダウンを行っている。
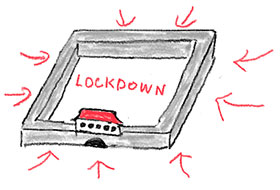 紀元700年頃、モンゴル軍に囲まれた城の中でバタバタ人が死んでいった。周りをモンゴル軍が囲っているから、伝染病は入りようがない。それなのに籠城が解けた後でも伝染病のような症状で多くの人が亡くなっていく。
紀元700年頃、モンゴル軍に囲まれた城の中でバタバタ人が死んでいった。周りをモンゴル軍が囲っているから、伝染病は入りようがない。それなのに籠城が解けた後でも伝染病のような症状で多くの人が亡くなっていく。
それを見た李東垣(りとうえん)は体の中から傷つけられるという内傷(ないしょう)という考え方で病気を治そうと補中益気湯を作った。
| 黄耆 | 元気を出す | 4g |
|---|---|---|
| 人参 | 元気を出す | 4g |
| 柴胡 | 炎症を抑える | 2g |
| 升麻 | 炎症を抑える | 1g |
| 蒼朮 | 4g | |
| 当帰 | 3g | |
| 陳皮 | 2g | |
| 大棗 | 味を良くする | 2g |
| 生姜 | 味を良くする | 0.5g |
| 甘草 | 味を良くする | 1.5g |
処方を見ると、免疫を上げて元気を出す黄耆と人参が入っている。さらに炎症を抑える柴胡と升麻も入っている。体力を上げながら炎症を抑える処方だ。 大棗、生姜、甘草はどの処方にも入っている生薬で、煎じ薬を飲みやすくするものだ。蒼朮、当帰、陳皮は何のために入っているかは李東垣に聞かねば分からない。
補中益気湯は元気を出す薬として使われている
李東垣が経験したような城攻めは普通の状況では起こらない。だから補中益気湯は、文字どおり益気(元気を増す)薬として使われてきた。
元気を出すのは黄耆と人参で、黄耆は多いときは1両(30gほど)必要なこともある。
脱肛と升提(しょうてい)作用
補中益気湯に含まれる柴胡、升麻、黄耆の3つの生薬を組み合わせると筋肉の収縮が良くなり、脱肛を治すと言われてきた。肛門を締めている肛門括約筋が加齢で弾力がなくなり、排便をする度に腸が肛門から出てしまう。これを脱肛という。
漢方では筋肉を丈夫にして持ち上げる作用を升提作用と言い、煎じ薬で治療している先生たちは、補中益気湯の中のこの3つの生薬を増やして治療していた。補中益気湯の成分の大棗、生姜、甘草は味を調整するために煎じ薬の中に入っているだけだが、これらを省いてしまうと飲みにくくなる。だから補中益気湯の升提作用は柴胡、升麻、黄耆の3つだけだと信じていた。
柴胡と升麻には升提作用がない
【漢方処方の臨床応用】(THE KANNPO叢書1. 1986年)の対談の中で 四川省中医学研究所の陸幹甫(りくかんぽ)先生が「升麻と柴胡にはその作用がなく、数百ある生薬の中で升提作用があるのは人参と黄耆にしかない」と断言するシーンが出てくる。
そうすると出席していた日本を代表する漢方医たちが、「えーっ」と言って驚いた様子が書かれている。当時の日本の漢方医にはなかった知識だからだ。
柴胡、升麻、黄耆の丸薬を作る
私が専門にしている丸薬は、味の問題を気にする必要がない。
そこで私は柴胡、升麻、黄耆だけの丸薬を作り升提丸と名付け、脱肛の患者さんに投与してきた。すると、確かに升提作用があり、よく効いた。この3つの生薬の分量は元の補中益気湯の生薬合計量の30%だから少しの量でよく効くのだと思った。
黄耆・人参丸での追試
元気を出すための薬なら補中益気湯の中の柴胡や升麻は必要ない。また生姜、大棗、甘草もいらないし、蒼朮や陳皮なども必要ないから黄耆と人参だけになる。これも補中益気湯の重さの30%になる。
使ってみると少しの量で疲労によく効く。ちょうど黄耆・人参丸があったので、脱肛の人に使ってみたらよく効いた。つまり、升麻と柴胡は升提作用に必然のものではないことが分かったのだ。
煎じ薬と丸薬
生薬は丸薬でも散剤でも使えると中薬大辞典に書いてある。だが丸薬と煎じ薬では必要量が違う。丸薬の方が生薬量は遥かに少なくてすむ。煎じ薬は有効成分がすべて抽出されず煎じカスの中に残るからだろう。
もし升麻や柴胡が升提作用に必要ないと考えると、升提丸の中で効いていたのは黄耆しかないということになる。黄耆は元気を出す目的で使うなら、多量に使わないと効かないこともある。
私が作った升提丸に含まれる黄耆は6gくらいだ。そうなら黄耆の升提作用の必要量と元気を出す時の必要量が違うのかも知れない。生薬の量は、病気の種類、体質などによって変えなければならない。
保険診療をしていては、生薬の組み合わせも投与量も変えることが出来ないから補中益気湯の升提作用も柴胡、升麻、黄耆と想像しながら使っていたのだろう。
- 第261回「補中益気湯(ほちゅうえっきとう)の解析」
- 2022年12月20日
香杏舎ノート の記事一覧へ

患者さまお一人お一人にゆっくり向き合えるように、「完全予約制」で診察を行っております。
診察をご希望の方はお電話でご予約ください。
- 読み物 -
- ●2026.02.01
- 121.腹水
- ●2026.01.25
- 第355回「日本は原子力潜水艦を持つべきだ」
- ●2026.01.20
- 第354回「DICに牛黄は使えないか?」
- ●2026.01.01
- 第353回「ラクダ、馬、象にも乗ったことがある」
- ●2025.12.25
- 第352回「夜の散歩という絵」
お知らせ
- ●2025.10.28
- オステオパシーの勉強会
- ●2025.05.02
- 背骨ローラーの販売について
※ページを更新する度に表示記事が変わります。










