第129回「老人は駅を目指す」
ここ20年続いたデフレのせいで住宅価格はピーク時の三分の一まで下落してしまった。
ところが東京にはまったく下落していないマンションが幾つもある。
そんなマンションの一つが広尾にある広尾ガーデンヒルズで30年前に1億ほどで売り出されたが、今でも当時以上の価格で売買されている。こういった価値の下がらないマンションはビンティッジマンションと称されて分譲当時の値段かそれ以上の高値で取引されている。
どうして価格が下がらないのだろう?
理由は幾つもあるが、まず都心には大規模開発できる土地がないこと、東京だけは人口が増加していること、さらに都心のマンションの値段が少しでも下がると、都心回帰現象がおこるのがその理由だ。
では他の都市では住宅価格が下がっていないマンションはあるだろうか?
関西では芦屋のラポルテ西館だけが唯一値段が下がっていないという。
芦屋は全国にも知られた高級住宅地で、山の手にはお金持ちの邸宅が立ち並んでいる。ラポルテ西館はJR芦屋駅に隣接したマンションで、市の分譲マンションだから高級なマンションではない。
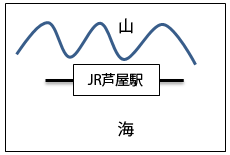 JR芦屋駅に降り立つと北側には山が迫り、急な上り坂になっている。
JR芦屋駅に降り立つと北側には山が迫り、急な上り坂になっている。
駅前の広場にはタクシーが多く留まっていて駅には200台ものタクシーがあり、乗車率は日本一だという。坂が急だから山沿いに住む山芦屋や六麓荘の住人がタクシーを頻繁に利用している。
ラポルテ西館はどうして売れているのだろう?不動産屋で話を聞くと、山の手に住んでいるお金持ちがラポルテ西館を買っているそうだ。
お金持ちは閑静な山の手の邸宅を好むのに何故なのだろう?
住人に聞いてみた。やはり不便なのだと言う。夏の夜にアイスクリームが食べたくなると、家族でジャンケンして誰が車を運転してアイスクリームを買いに行くか決める。高級住宅地にはそんな不便さがある。
年寄になると運転も面倒になるので、駅の近くに住みたい。なるほど芦屋駅にはデパートの大丸を核とするショッピングモールがあり、大きな駐車場もある。神戸に行くにも大阪に行くにも新快速に乗れば15分ほどだ。人口の老齢化が駅近のマンションの値段を上げていたのだ。
他の場所でそういう地域はないのだろうか?新築時の販売価格を上回るまでの上昇はないが、大阪郊外の高槻、茨木駅の駅周辺のマンションは同じ理由で上がっている。
東京でもそんなことが起こっていないのだろうか?
残念なことに関東平野は起伏が激しく芦屋のように単純な地形になっていない。地名を見ても渋谷や代官山、白金台といった高さを示す言葉が入っていることからも起伏のある地形を想像できる。そんなわけで地形からの解析は難しいし、ショッピングモールのある場所も一定ではない。
またビンティッジマンションのロケーションからもそういった傾向はみられなかった。
長く続くデフレは住宅価格を押し下げるだけでなく、住宅地から小さな商店を無くしてしまった。客単価の低い商売で食っていくには客数が重要になる。マクドナルドや吉野家が住宅地で営業できるはずもない。
昔のように住宅地の中の魚屋、八百屋、クリーニング店は消えてしまい、医院や歯科医院さえなくなってしまった。
そういった業種はすべて人の多い駅前に集まっている。銀行、コンビニ、スーパー、美容院などすべての業種が駅前に集合して、住宅地はライフラインに必要な物がない砂漠のような存在になり、反対に駅周辺がオアシスのような存在になっている。
多摩ニュータウンなどでは買い物難民などという言葉も囁かれているが、実際に過疎化したところには生活に必要な物がなくなってしまった。
駅前といっても様々な形態がある。古い商店街がありシャッターが下りているなら駅前でもオアシスとは呼び難い。スーパーやコープがあれば一安心だがファーストフードの店があればオアシスと呼ぶにふさわしい駅前だ。コンビニも一定数の客が見込める所にしか店を出せないから、必然的に乗降客の多い駅の近くか幹線道路沿いにある。
老齢化が進み、老夫婦か、それとも一人暮らしになると、買い物や食事が面倒になる。近くにスーパーやコンビニがあれば惣菜を買って簡単に食事を済ますことができる。
こういったライフラインが集まる駅の中で最高位にランクされるのは、スターバックスコーヒーがある駅だ。単価の高いコーヒーを買う富裕層が多く住む地域でしか開業できないので、駅周辺には富裕層が多く住んでいる。
便利に暮らすためには、山の手の高級住宅地という概念を捨てなければならない時代になった。不動産屋は「昔は駅から徒歩10分までと言われたが、私は5分以内と言いたい。特に1分以内の物件が貴重だ。だって5分以内の物件に比べて面積的には25分の1しかないから」と言う。
老人の増加に従って駅前のマンションはこれからもっと高くなっていくに違いない。
- 第129回「老人は駅を目指す」
- 2013年08月20日
香杏舎ノート の記事一覧へ

患者さまお一人お一人にゆっくり向き合えるように、「完全予約制」で診察を行っております。
診察をご希望の方はお電話でご予約ください。
- 読み物 -
- ●2026.02.01
- 121.腹水
- ●2026.01.25
- 第355回「日本は原子力潜水艦を持つべきだ」
- ●2026.01.20
- 第354回「DICに牛黄は使えないか?」
- ●2026.01.01
- 第353回「ラクダ、馬、象にも乗ったことがある」
- ●2025.12.25
- 第352回「夜の散歩という絵」
お知らせ
- ●2025.10.28
- オステオパシーの勉強会
- ●2025.05.02
- 背骨ローラーの販売について
※ページを更新する度に表示記事が変わります。










